
3歳の息子は発達障害グレーゾーンです。3歳10ヶ月になる4月から区の療育に通園することが決まりました!
↓息子が生まれてから発達障害だと認識するまでの様子はこちらから
市区町村の療育に通園したい場合の手順
今回は「市区町村の療育(児童発達支援)に通いたいがまず何をすればいいの?」という話です。私の経験を通してお話できればと思います。
相談
まずは、お住まいの市区町村の障害福祉課、児童福祉担当窓口、または児童発達支援センターなどに相談します。お子さんの発達の状況や、療育の必要性について相談しましょう。
私の場合は、近くの保健相談所に『言葉の相談』があったため、電話してまずは相談をしました。
ここで療育の必要性があると判断された場合は、市区町村の療育の紹介をしてもらうという流れでした。
一般的に2歳以降になれば診断をつけることも可能なのですが、3歳になるまでは「様子見」とするところも多いようです。
医療機関の受診(必要な場合)
自治体によっては、医師の診断書や意見書が必要となる場合があります。相談窓口で指示があった場合は、小児科医や児童精神科医などの医療機関を受診し、診断や意見書を作成してもらいましょう。
ただし、この段階では必要ないことも多いです。特にグレーゾーンが疑われる場合は診断の必要性がない場合もあります。それは、診断をつけることでその子の困ったが軽減されるのであればつけた方がいいですが、それに当てはまらない場合はメリットがないと判断されることもあるからです。
療育先で発達検査
一般的に、紹介された市区町村の療育先でまずは発達検査が行われます。
この結果を踏まえて、「相談事業」「訪問支援事業」「児童発達支援事業」の利用が決められます。
相談事業
「相談事業」は受給者証がなくても受けられるサービスで、月1回など定期的に子供の様子を見てもらい相談するという事業です。
訪問支援事業
受給者証が必要です。
通っている保育施設に専門知識のある職員が訪問し、子供の様子を見て、保育施設側と親に共有してくれるサービスです。
児童発達支援事業
受給者証が必要です。
こちらが皆さんが想像している「療育」となります。子供が通園して、集団生活を学んだり、個別の指導をしてもらえるサービスです。
基本的には年度単位での利用となり、4月〜3月までの期間です。その他のタイミングでの利用となると、空きがあれば入れる、という状況になるかと思います。
受給者証の申請
受給者証が必要なサービスを受けたい場合には、市区町村の窓口で「障害児通所受給者証」の申請手続きを行います。
その際に必要なものは以下のとおりです。
- 支給申請書
- 医師の診断書または意見書(必要な場合)
- 療育手帳または障害者手帳(お持ちの場合)
- お子さんと保護者のマイナンバーが確認できるもの
- その他、自治体が必要とする書類 (世帯の所得状況を証明する書類など)
申請の際は市区町村の療育から「必要である」と判断を受けたことが前提となり、その判断を受けてから1年以内に申請をしなければなりません。※市区町村によって異なります。
市区町村の窓口からも療育先に確認がとられます。
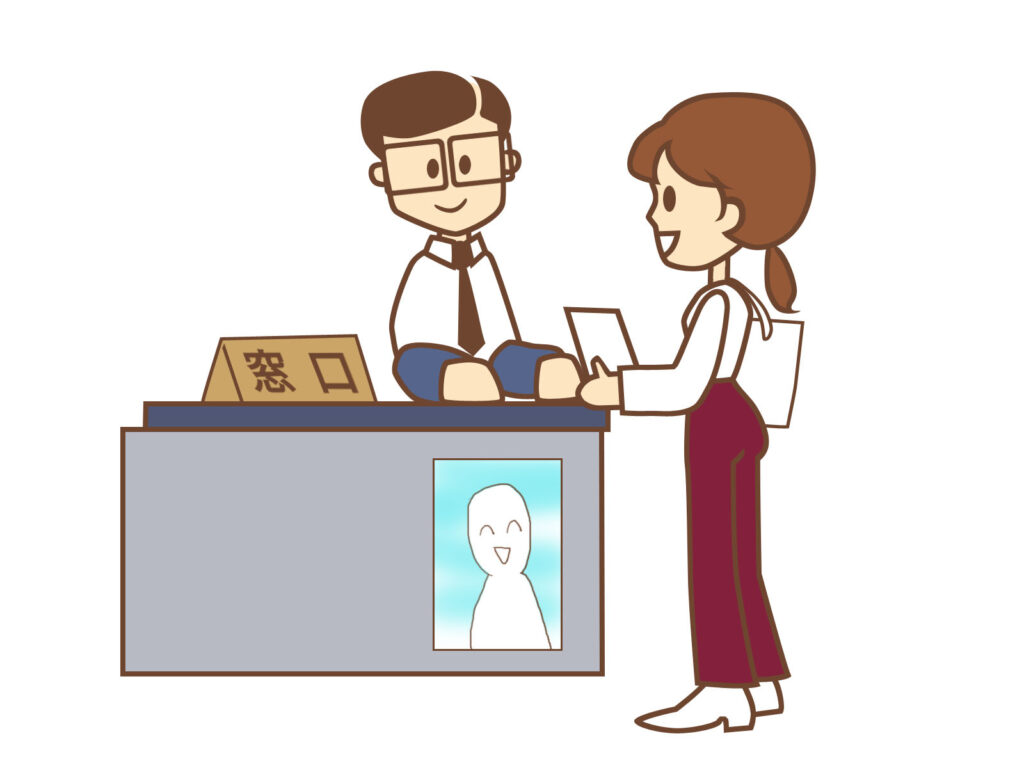

障害児支援利用計画案の作成
受給者証の申請と並行して、障害児支援利用計画案を作成します。これは、お子さんの状況や、どのような支援が必要かをまとめたものです。
- 相談支援事業所に依頼して作成してもらう
- 保護者自身で作成する(セルフプラン) どちらかを選択できます。相談支援事業所に依頼する場合は、相談支援専門員が面談を行い、計画案を作成します。
私は迷わず依頼して作成してもらいました!
市区町村による審査・決定
提出された申請書類や障害児支援利用計画案に基づき、市区町村が利用の必要性や支給量などを審査し、受給者証の交付を決定します。
受給者証の交付
審査が通ると、市区町村から受給者証が交付されます。
私の場合は、申請から交付まで約20日かかりました。

事業所(療育先)との契約
受給者証を持参し、利用する児童発達支援事業所と利用契約を結びます。利用日数や時間、支援内容などを確認し、契約を締結します。
ここでやっと療育先との契約ができ、晴れてサービスを利用することができます。
受給者証があれば民間の療育も利用可能に
受給者証があれば、市区町村の療育だけではなく、民間の療育も利用が可能になります。
詳しくいうと、受給者証がなくても民間の療育利用は可能ですが、全額負担となります。受給者証があれば1割負担(3歳児クラス以上は負担なし)になります。
民間の療育は土日祝日も対応しているところが多く、両方併用している人も多くいます。
↓実際に民間療育を探してみた様子はこちら
学研のあいうえおタブレットがお気に入りで、これでひらがな覚えました!


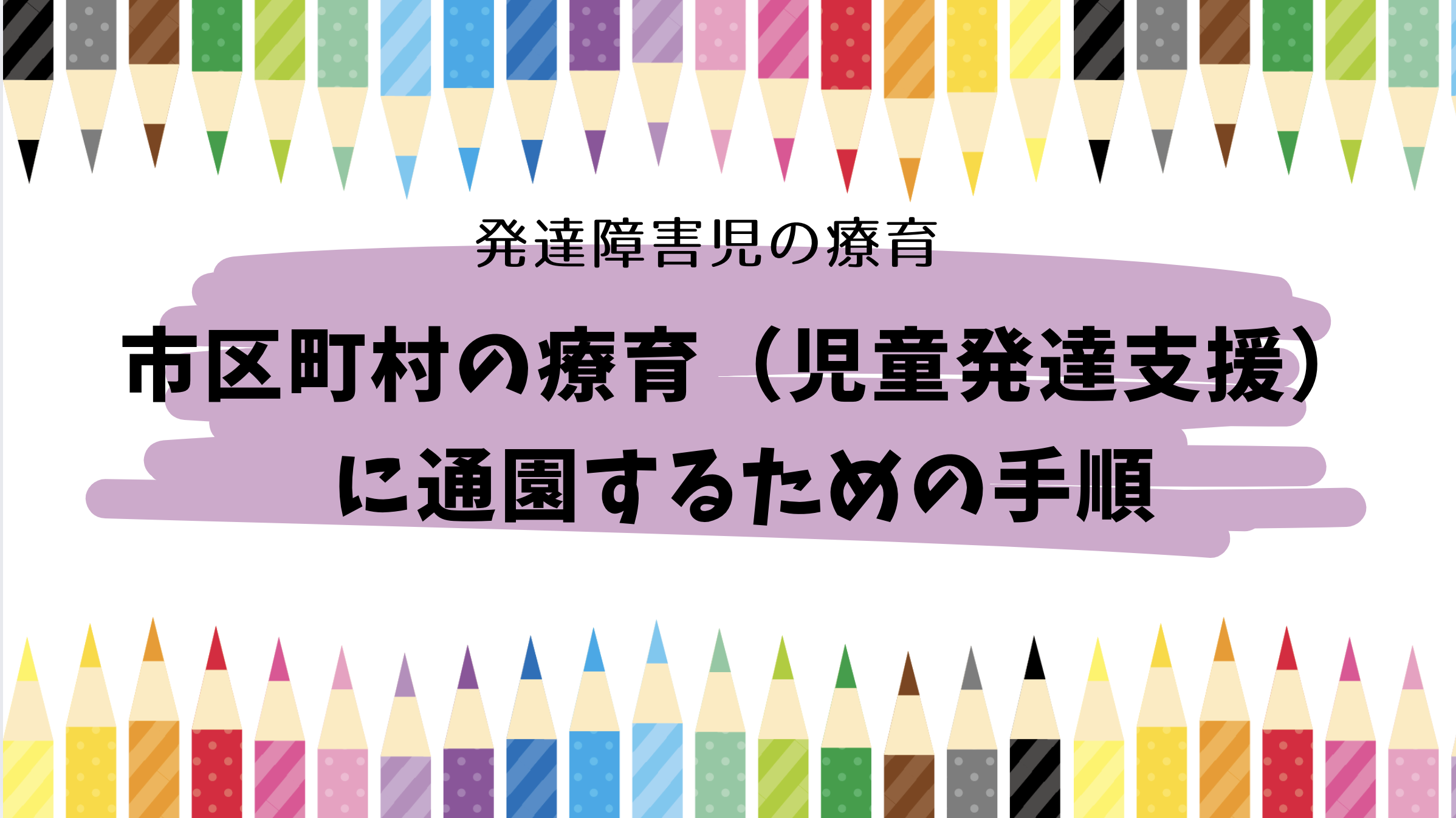
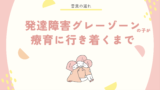

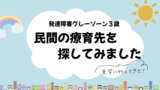

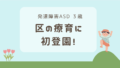
コメント