
3歳の息子は自閉スペクトラム症と診断されました。でもそもそも発達障害ってどういう種類があるのでしょう?
発達障害とは先天性の脳機能の障害
「発達障害」は、生まれつきの脳機能の発達の偏りによって、幼児期から行動や情緒面に特徴が現れ、日常生活や社会生活に困難が生じる状態を指す包括的な概念です。外見からは分かりにくいことも多く、その症状や困りごとは人それぞれ異なります。
はい、今は「発達障害は先天性の脳機能の障害」と定義されているのですね。
発達障害者支援法
また、法律「発達障害者支援法」での定義は以下のとおりです。
この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
息子が診断された時も、生後30ヶ月内の症状から診断されました。これは”低年齢時において発現するもの”と定義されているからなのですね。
発達障害の種類
現在、国際的な診断基準であるDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)では、「神経発達症群(Neurodevelopmental Disorders)」として分類され、以前用いられていた分類とは一部変更があります。
DSM-5における主な発達障害の種類は以下の通りです。
自閉スペクトラム症(ASD)
自閉スペクトラム症・自閉症スペクトラムなどと言われます。
以前の「自閉性障害」「アスペルガー症候群」「特定不能の広汎性発達障害」などがこの自閉スペクトラム症(ASD)に統合されました。
特徴としては、社会的なコミュニケーションと相互作用の持続的な困難、限定された反復的な行動・興味・活動などがありますが、症状の現れ方や重症度は非常に多様です。
高機能自閉症
改定後は、高機能自閉症も自閉スペクトラム症(ASD)に含まれます。
高機能自閉症は、知的発達の遅れを伴わない場合に用いられる言葉です。
知的発達に遅れがないため、一見するとコミュニケーションも円滑に見えることもありますが、コミュニケーションが取りづらかったり、空気を読むのが苦手で対人関係の構築が困難であったり、特定のこだわりがあったりします。
また、感覚の過敏さまたは鈍麻さを持つ場合もあります。音、光、匂い、味、触覚などに対して、過剰に敏感に反応することがあります(例:大きな音が苦手、特定の肌触りの服が着られない)。逆に痛みに鈍感である場合もあります。
アスペルガー症候群
現在はアスペルガー症候群も自閉スペクトラム症(ASD)に包括されています。
高機能自閉症の一種ともされており、知的発達の遅れや明らかな言葉の遅れがないASDの方の特性を指す言葉として使われています。
特徴としては、高機能自閉症とほぼ同じ特徴を持ちます。
乳幼児期は言葉の遅れがあるものの、遅れて言葉が発達します。
息子も自閉スペクトラム症のアスペルガー症候群だと言われましたが、確かに言葉の遅れはあったものの、今では他の子どもたちに追いつく勢いで、成長しています。
広汎性発達障害(PDD)
現在は自閉スペクトラム症(ASD)とよばれています。
改訂前はこの「広汎性発達障害(PDD)」という言葉が用いれれていました。ですが今でも過去に診断されたものを示す意味で使われることもあります。
注意欠如・多動症(ADHD)
自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠如・多動症(ADHD)には、知的障害が表れることがあります。
知的障害は知的機能や適応機能に基づいて判断され、軽度・中等度・重度・最重度に分けられます。
注意欠如・多動症(ADHD)の主な特徴は、不注意(集中困難、気が散りやすいなど) 、多動性(落ち着きがない、じっとしているのが苦手など)、衝動性(考えずに行動してしまう、順番を待てないなど) が年齢や発達に不釣り合いな程度で見られ、日常生活に支障をきたします。
学習障害(LD)
学習障害(LD)は、全般的な知的発達には遅れがないものの、特定の学習能力(読む、書く、計算するなど)の習得と使用に著しい困難を示す状態です。
就学前の幼児期は学習障害の特徴や症状が現れにくく、学校に入学してからは「教科書を読むのに時間がかかる」「文章を読んでも理解できない」「計算をひどく間違える」などのサインが見られることがあります。
知的な遅れがないことから周りに誤解されやすく、孤独を感じて二次障害(引きこもりや不登校など)を引き起こすこともあります。
いかがでしたでしょうか。
時代と共に発達障害の名称やその定義が変化しているのですね。
もし、ご自身やお子さんの発達について気になることがあれば、専門機関(医療機関の発達外来、児童発達支援センター、発達障害者支援センターなど)に相談することをおすすめします。
自閉スペクトラム症と診断された息子が、こちらの書籍を読んで実践し、みるみる成長しました!!

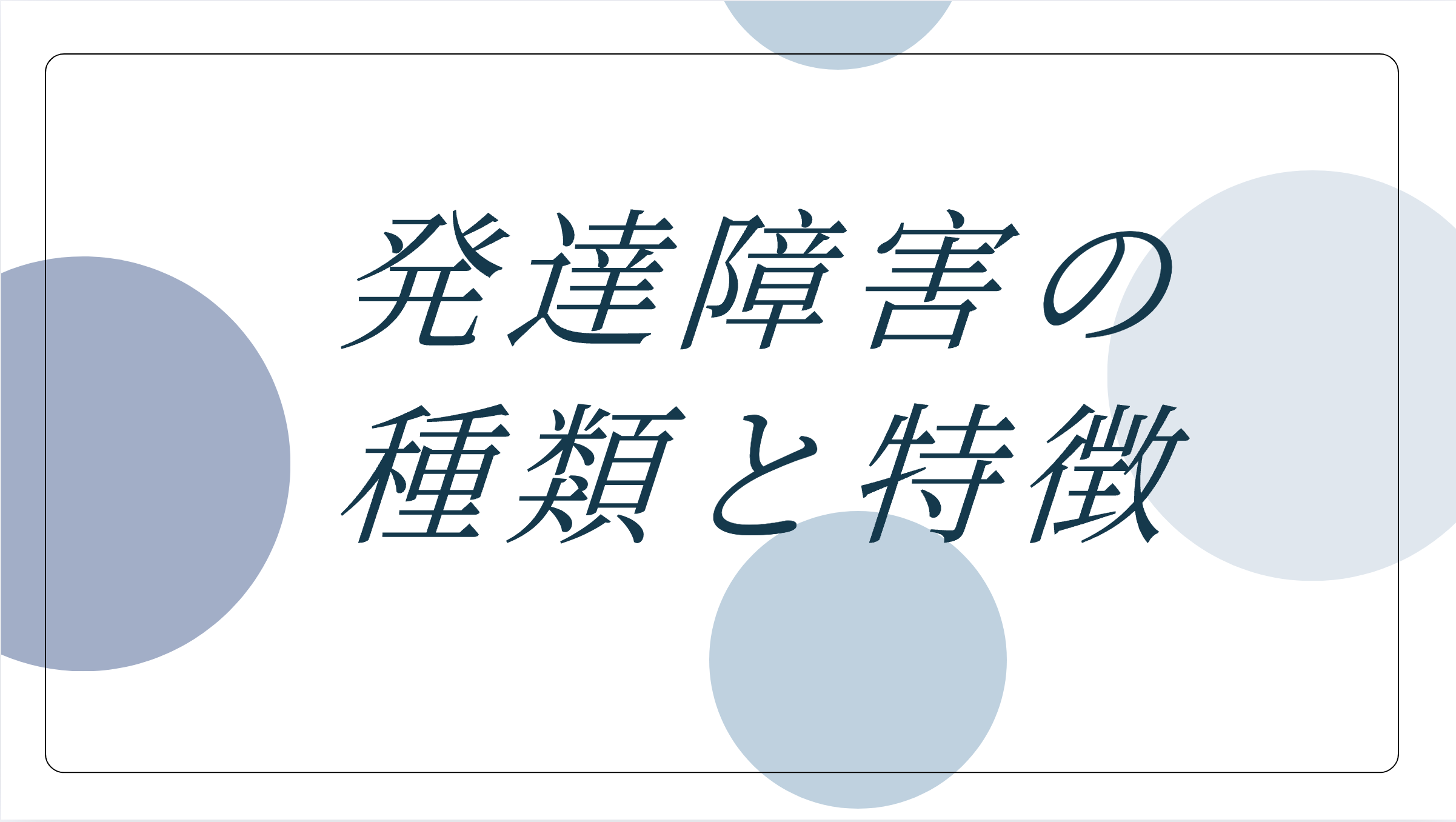

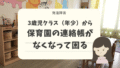
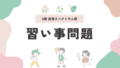
コメント