
3歳9か月の息子は言葉の遅れがあり発達障害グレーゾーン(自閉症スペクトラム疑い)です。
2歳5か月の発達検査では「様子見」と言われ、本当に様子見してしまったことを後悔しています。
↓療育に行きつくまではこちら
3歳までは診断をしない
息子の言葉の遅れが気になり、初めて保健相談所に相談したのが2歳5ヵ月のときです。専門の心理士さんが発達検査をしてくれ、「応答の指差しがない」と指摘されたものの「3歳まで様子を見ましょう」と言われました。
理由は、この時期の子供の成長スピードは速く、半年後には話し出してるかもしれない、ということでした。
「きっと今はいっぱいインプットしているんですよ」と励まされたりもしました。
2歳を過ぎれば診断もつけられるはずなのですが、暗黙の了解なのか、3歳までは様子見というところも多いのです。
私は何もわかっていないので、言葉通り、話し出すことを待つしかありませんでした。
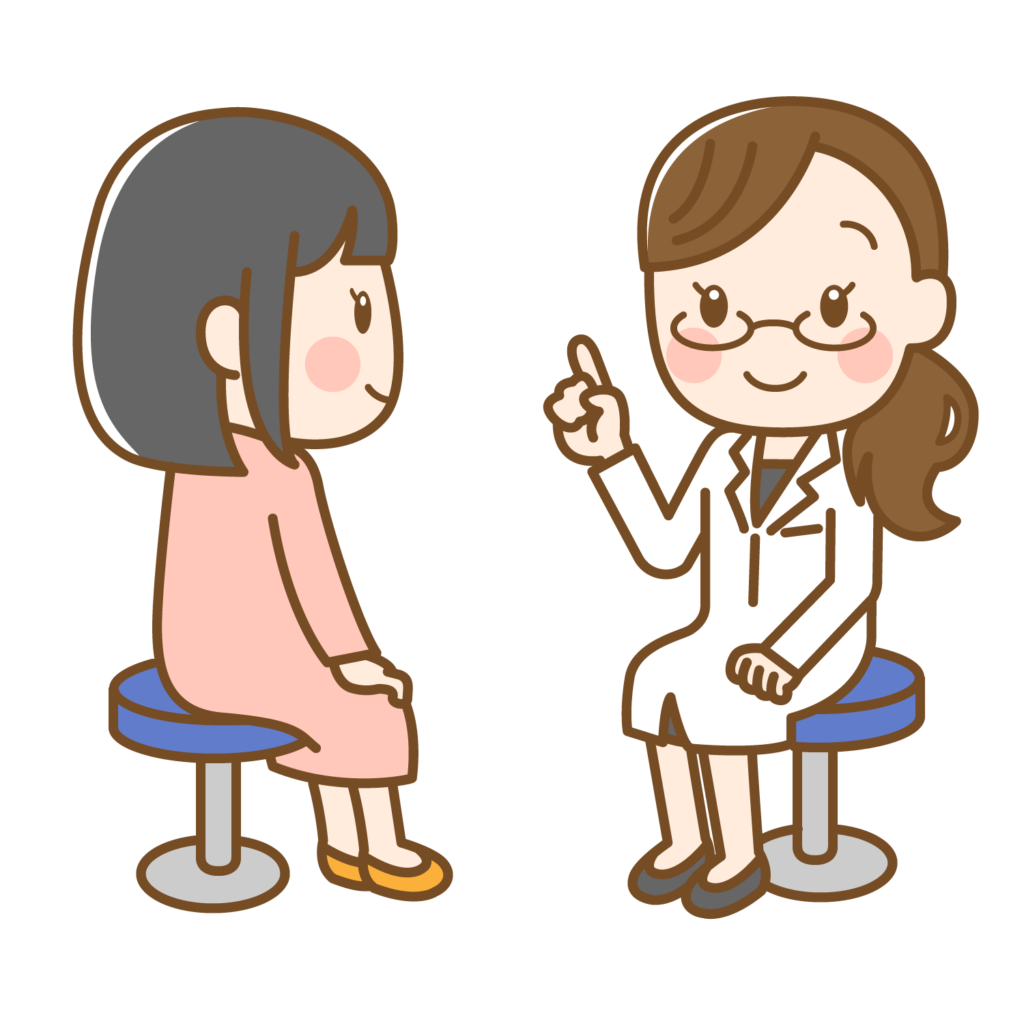
療育先は慣れている
3歳0ヵ月、2回目の保健相談所での相談の結果、「言葉だけの遅れ」があると言われ、児童発達支援センターの紹介をされました。
ここでは最初に詳しい発達検査「田中ビネー式」を行いました。結果は生活面での精神年齢が半年の遅れ。
そして、月1の相談事業を利用することになりました。
この相談事業の内容は簡単な発達検査と相談で、所要時間は1時間程度のものなのですが、いつも「段々話せるようになってきましたね!」と言われるだけで、このまま様子見という結果に落ち着くのです。
特に「家庭でこういうことに取り組んだ方がいいですよ」などのアドバイスはなく、またどのくらい深刻な状況だとか、そんな話もないのです。
おそらく、児童発達支援センターの人たちは発達障害の子に慣れているので、いわゆるグレーゾーンの子たちは「まだ軽い」という認識なのだと思います。
でも私は児童発達支援センターの人が言うならそうなのだろうと鵜吞みにし、またここでも様子見という放置をしてしまうのです。
今から思うと、現実を見たくない、きっと息子は普通になる、ある日突然しゃべりだすんだ!という気持ちも大きかったのだと思います。
実際まわりの人たちからは「男の子は言葉が遅いから」「うちの子は言葉の爆発期が来て今はペラペラしゃべってるよ」という話を聞いていたので、なおさらそう思ったのでしょう。
誰だって、可愛いわが子が発達障害だなんて思いたくないですもんね。

誰も何も教えてくれない
もし我が子が発達障害かもしれなくても、その対応方法は誰も教えてくれません。
どこに相談にいくべきなのか、療育に行くにはどうしたらいいのか、どのくらいかよえばいいのか、受給者証ってなに?療育手帳ってなに?発達検査ってどこでしてくれるの?費用はどのくらいなの?家では何をすればいいの?
育児書のような教科書も存在しません。なので知らないことを質問しなければなりませんが、誰に何を聞いたらいいのかもわかりません。
そしてやっとのことで相談できても、そこでの相談結果が正しいのかどうかはわからないのです。
こうして何もできずに時間だけが過ぎていきます。

保護者の選択が重視される
我が子が発達障害の症状があるか、どれほど深刻な状況なのか、ちゃんと判断できる保護者はどのくらいいるのでしょうか。
たいていの場合はわからない保護者が多いのではないでしょうか
初めての育児ならばなおさらです。ほかの比較対象する子供がいないのですから、当然です。
なので、保育園や幼稚園の入学面接で発達障害を指摘されるケースも多いようですね。
保育園や幼稚園もハッキリは言わない
でもですね、保育園も幼稚園も保護者の気持ちを考えてくれているのか、ハッキリは言わないんですよね。※明らかに症状がある場合は除きます。
なので余計に保護者はことの深刻さに気が付かないのです。
ひどい保育園・幼稚園だと、「発達障害なら退園してくれ」とフォローもなく切られるだけのところもあるようです。※ママ友が実際に経験したそうです。
児童発達支援センターも積極的にはすすめてこない
児童発達支援センターにおいても、保護者が積極的に療育を受けたい!と言わない限りは先方が積極的にすすめてくることはありません。
私も「言葉だけではなく、集団生活も不安なんです」と訴えてやっと療育の応募をすることができました。
※療育も応募数が多く、狭き門と言われるほどなので仕方がないのかもしれませんが。。。
療育の応募ができたところで、今度は子供にはどのくらいの頻度で通園して、どんなコースがいいのか、がわかりません。
私は最初、なんとなく半日コース月1回で応募してしまいましたが、不安になり電話で相談してみると「お子さんの場合月1では少ないですね」と言われ、慌てて週1に変更した経緯があります。あの時電話で相談していなかったらと思うとぞっとします。
保護者が積極的に働き掛けない限り、保育園も児童発達支援センターも積極的には動きません。
これは基本的に保護者の意思・選択が尊重されるためです。
3者が協力してチームを作る 『訪問支援事業』
よく、保育園や幼稚園・療育・保護者が協力してチームを組むのがいい、と言われますが、本当にその通りだと思います。 児童発達支援センターには『訪問支援事業』という、お子さんの通う保育園や幼稚園に専門のスタッフが訪問・子供の様子を見て、保育園や幼稚園と共有、保護者への報告をしてくれるサービスもあります。
ぜひ利用してみてください。
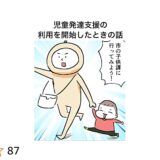
書籍『言葉の遅れを改善する本』を読んで後悔
この書籍は、乳幼児期のテレビやスマホの長時間視聴により自閉症の症状を発症する『新しいタイプの言葉の遅れ』が存在する、と学会でも発表された論説を紹介しています。
このタイプにはスマホやテレビなどのメディア断ちをし、親子のコミュニケーションを密にすることで改善する、と事例をあげて示しています。
ただし、推奨するのは2歳まで、遅くても3歳までに実践すべきだと提唱しています。
これを読んで、「様子見」なんて真に受けずに、もっと早くちゃんと対応しておけばよかったと激しく後悔しました。
現にこの書籍にも『要観察といわれたら放置してはいけない』と書かれているのです!
時は戻せません。
今やれることをやるしかないとは思いますが、知識や情報がないばかりに子供の人生が取り返しのつかないことになってしまうことだけは、頭の片隅に置いていただければと思います。


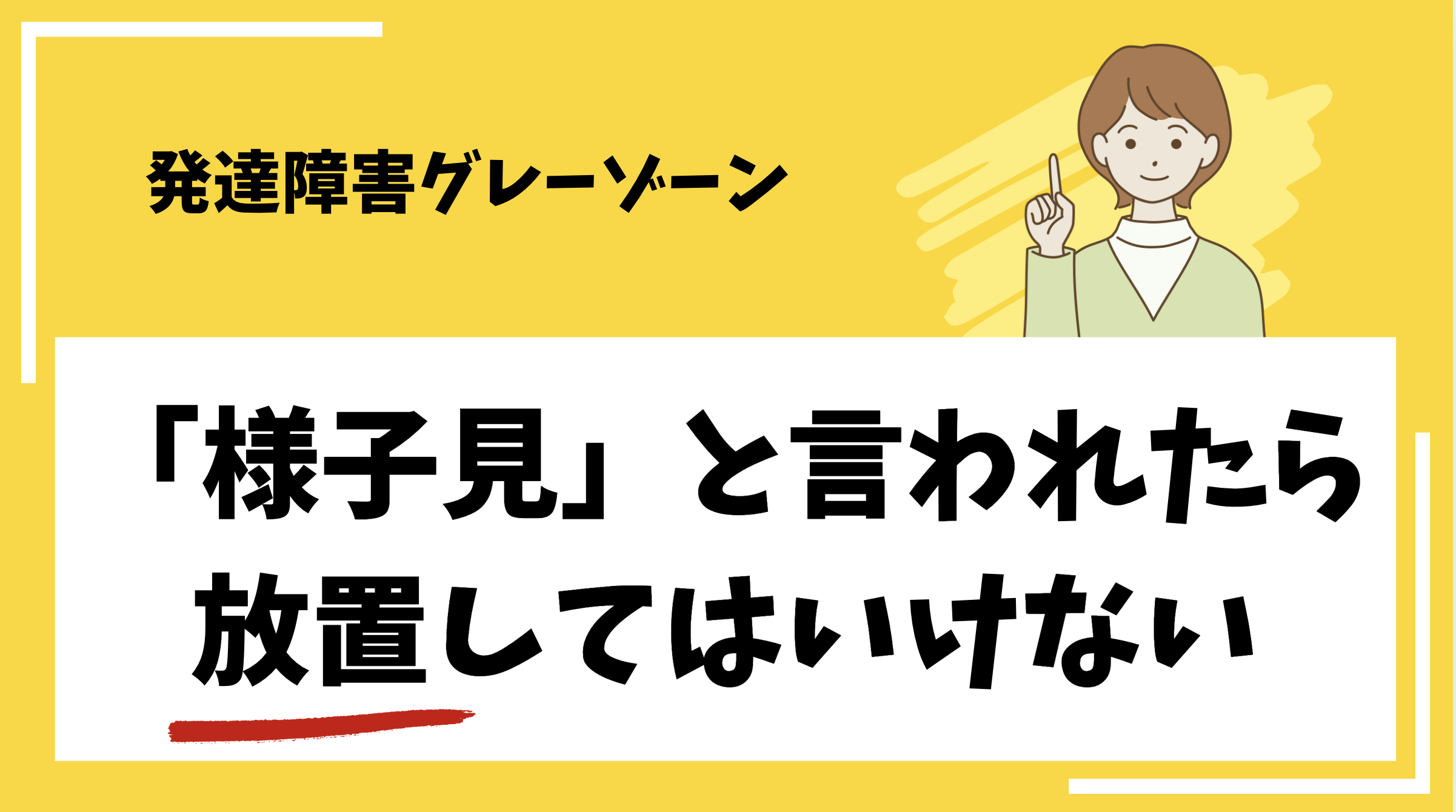
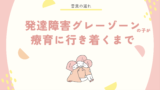



コメント