
3歳11ヶ月の息子は自閉スペクトラム症(ASD)です。発達障害の疑いがありそれを受け入れるまでが、孤独で一番辛かったです。
子供の発達障害なんて受け入れられないですよね
今でこそ、息子の発達障害・自閉スペクトラム症(ASD)であることを受け入れて前向きに動いていますが、ここまでの道のりはとても辛いものでした。
誰だって、愛する自分の子どもが発達障害だと言われたら、受け入れられないでしょう。
私の場合、息子が3歳8ヶ月になるまで、発達障害であることを受け入れられず、誰にも言えず、ずっと孤独でした。
どこに相談に行っても『様子見』と言われるだけだったので、「きっといつか普通になるんだ!信じなきゃ」と思ってました。
きっと、同じような保護者の方がたくさんいるんじゃないかな、と思い、何か役立てることはないか、とこの記事を書いています。
受容のステップ
子供の発達障害を親が受容するときの進み方には、代表的な理論として「段階説」と「慢性的悲観説」があります。 ※出典:子ども発達障がい支援アドバイザーテキスト
段階説
これは、人が大きな喪失や困難な出来事に直面したときに経験する心理的なプロセスを、いくつかの段階に分けて説明しようとする考え方の一つです。子供が発達障害であるという診断は、親にとって非常に大きな出来事であり、様々な感情が湧き起こるため、この「段階説」が親の心の動きを理解する一つの参考として用いられることがあります。
代表的な「段階説」では、以下のような心の動きの段階が示されることが多いです(提唱者や研究によって、段階の数や名称、順番は多少異なります)。
- ショック期(Shock)
- 診断を告知されたり、子どもの発達に何か問題があるのではないかと気づいたりした最初の時期です。
- 頭が真っ白になったり、現実感がなくなったり、何も考えられないような状態になることがあります。
- 精神的な打撃が大きく、呆然としてしまう段階です。
- 否認期(Denial)
- 「何かの間違いではないか」「うちの子に限ってそんなはずはない」「信じられない」というように、現実を受け入れたくない、認めたくないという気持ちが強く働く時期です。
- 他の医師の意見を聞きに行ったり、情報を集めたりする中で、診断を否定しようとすることもあります。これは、あまりにも大きな衝撃から自分を守ろうとする心の働きとも言えます。
- 混乱期(Turmoil)
- 否認しきれなくなり、様々な強い感情が次々と現れて混乱する時期です。この段階には、以下のような感情が含まれることがあります。
- 怒り(Anger): 「なぜうちの子が?」「誰のせいなんだ?」といった怒りの感情が、医師や配偶者、あるいは自分自身に向けられることがあります。
- 悲しみ(Sadness): 子どもの将来に対する不安、期待していた子ども像との違いに対する喪失感、深い悲しみに襲われます。涙が止まらなくなることもあります。
- 罪悪感(Guilt): 「自分の育て方が悪かったのではないか」「妊娠中の過ごし方が原因ではないか」などと、自分を責めてしまうことがあります。
- 抑うつ(Depression): 無力感や絶望感を感じ、何もする気が起きなくなったり、気分がひどく落ち込んだりすることがあります。
- 否認しきれなくなり、様々な強い感情が次々と現れて混乱する時期です。この段階には、以下のような感情が含まれることがあります。
- 適応期・再起期(Adaptation / Reorganization / Acceptance)
- 混乱期を経て、少しずつ現実と向き合い、子どもの障害を理解しようと努め始める時期です。
- 子どもの良いところや可能性に目を向けられるようになったり、必要な支援や関わり方について具体的に考え始めたりします。
- 障害のある子どもと共に、新しい生活や親子関係を築いていこうという前向きな気持ちが芽生えてきます。
- 「受容」という言葉が使われることもありますが、これは必ずしも障害を完全に肯定し、全ての悲しみが消えるという意味ではなく、障害のある子どものありのままの姿を受け止め、共に生きていく覚悟や意味を見出していくプロセスと捉えられます。
「段階説」を理解する上での大切なポイント
- 個人差が大きい: すべての親御さんが、この段階を順番通りに、同じ期間で経験するわけではありません。ある段階を長く経験する人もいれば、特定の段階をあまり感じない人もいます。
- 行ったり来たりする: 段階は一方通行ではなく、状況や気持ちの変化によって、前の段階に戻ったり、複数の感情が同時に存在したりすることもあります。
- 「受容」がゴールではない: 「早く受容しなければ」と焦る必要はありません。それぞれの親御さんのペースで、気持ちと向き合っていくことが大切です。
- 発達障害の特性による影響: 発達障害は、診断がつくまでに時間がかかったり、成長とともに特性の現れ方が変化したりすることもあるため、この「段階説」が必ずしも全てのケースに当てはまるとは限りません。

慢性的悲観説
子供が発達障害であることに対する親の心の動きを説明するもう一つの考え方として「慢性的悲観説(まんせいてきひかんせつ)」、あるいは「慢性的悲哀説(まんせいてきひあいせつ)」があります。
これは、1960年代に**オルシャンスキー(Olshansky)**という研究者によって提唱された考え方です。
簡単に言うと、**「子どもの障害に対する親の悲しみや苦悩は、一度『受容』すれば完全に消え去るものではなく、生涯を通じて持続し、様々なきっかけで繰り返し現れる、ある意味で自然な感情である」**とする説です。
「段階説」が、ショックや否認といった段階を経て最終的に「受容」や「再起」といった安定した状態に至るプロセスを描くのに対し、「慢性的悲観説」は、その悲しみが波のように寄せては返し、完全にはなくならないという側面に注目しています。
慢性的悲観説の主なポイント
- 悲しみの持続性・反復性:
- 子どもの障害の現実を受け入れた後も、ふとした瞬間に悲しみ、喪失感、怒り、不安といった感情が繰り返し湧き上がってくることがあります。
- これは、親御さんの心が弱いからとか、受容できていないからというわけではなく、特別な状況に対する人間として自然な反応だと捉えます。
- 悲しみが再燃するきっかけ:
- このような感情は、特に以下のような時に再燃しやすいと言われています。
- 子どもの成長の節目: 周りの同じ年齢の子どもたちが新しい発達段階に進むのを見たとき(例:言葉を話し始める、自転車に乗れるようになる、友達と遊ぶ、進学する、就職するなど)。
- 期待と現実のギャップ: 親が抱いていた子どもの将来像と、現実との間にギャップを感じたとき。
- 新たな困難や課題の発生: 子どもの新たな問題行動や、療育・教育・医療に関する新しい課題に直面したとき。
- 社会的な障壁: 周囲の無理解や偏見に傷ついたとき、社会参加の難しさを感じたとき。
- 子どもの状態の変化: 子どもの体調が悪化したときや、新たな診断が加わったときなど。
- このような感情は、特に以下のような時に再燃しやすいと言われています。
- 「受容」の捉え方:
- この説における「受容」とは、必ずしも悲しみが完全に消え去り、常に前向きでいられる状態を指すわけではありません。
- むしろ、悲しみや困難を抱えながらも、子どもへの愛情を持ち続け、その子どものありのままの姿と共に生きていくこと、その悲しみと共に人生を歩んでいくことを意味合いとして含んでいると考えられます。

今までの苦しみ期、受け入れ期
息子の発達障害 経緯
発語は1歳6ヶ月
そこから徐々に言葉が失われていく
2歳5ヶ月 保健相談所に相談、発達検査。結果、様子見。
2歳8ヶ月 徐々に言葉が戻ってくる ⇨折れ線型自閉症の可能性
3歳0ヶ月 再度保健相談所で発達検査 ⇨区の療育を紹介してもらう
区の児童発達支援(療育)で相談事業の利用開始 でもずっと様子見。
3歳8ヶ月 保育園にお願いして、同じ療育に通う子供のママさんを紹介してもらう。⇨やっと苦しみから解放されました!
3歳10ヶ月 区の児童発達支援で療育通園開始、民間の療育通園開始
児童神経科にて軽度の自閉スペクトラム症(ASD)の診断あり
検索魔と化していた 発達障害を受け入れられない期
まず、息子は言葉が遅れていたことが発達障害を疑うきっかけとなりました。
なかなか発語しなくて心配だったのですが、1歳半でやっと発語(ワンワン、バイバイなど)してとても安心しました。
ところが、それから言葉が増えるどころか、徐々に失われていきました。
この時が一番、私が情緒不安定で、毎日毎日インターネットで検索していた日々でした。
息子に当てはまることがあればショックを受けて凹み、当てはまらないことがあれば安心していました。
今から思えば、当てはまらないことを探して安心したかったのだろうと思います。「息子は絶対普通なんだ、発達障害なんかじゃない!」って思いたかったんですね。
周りからも「男の子は言葉が遅いから」「いきなり話し出すらしいよ(爆発期)」などと言われ、私がきっと心配しすぎなだけかも。。。なんて思ったり。
当時はチェックリストや同じ症状の子ばかり検索していた
当時検索していたものと言えば、自閉症のチェックリストです。
そしてYouTubeでは、息子と同じ症状の子ばかり探していました。その子が自閉症と診断されていると凹み、回復している子がいれば希望を持って、の繰り返しでした。
受け入れられている今だから後悔しているのですが、「検索するものが違うよ!」と当時の自分に突っ込みたくなります。
なぜなら、専門員であっても判断が難しいのに、素人がチェックリストなんかで判断できるはずがない。そして発達障害はその子によってまるで症状が違います。同じ症状の子がいてもそれはほんの一部なのです(自閉スペクトラム症のスペクトラムとは連続体という意味からも症状の現れ方やその程度が、虹の色のようにはっきりと区切られているのではなく、連続的で多様であるという意味合いで使われています)。
もし戻れるなら、理解することから始める
今、あの時に戻れるなら、まずは発達障害について理解することから始めます。
今から思い返すと、「発達障害について何も知らなかった」から怖かったんだと思います。
ちゃんと知れば、そんなに怖いものではないのです。
そして、WebやYouTubeばかり検索することをやめます。
まず、書籍を読むこと。⇨なぜならWebやYouTubeはエビデンスがなくても公開できますが、書籍はエビデンスがある信頼できる情報の可能性(専門性)が高いからです。
そして気がつくのです。
不安だったのは、発達障害がどんなものなのか知らなかったからだ、と。
少しでも回復する方法があるのなら、早急にそれを実践するしかない。
チェックリストや同じ症状の子を検索して凹んでる時間があるなら、もっと勉強して、子供のために回復する方法を探し、実践する時間に充てるべき!!
発達障害は未解明な部分も多い
と言うのも、勉強している今だからわかりますが、発達障害というのはまだ未解明な部分も多く、根本的な治療方法は確立されていません。
一応、自閉症は先天的な脳機能の障害であると定義されてはいますが、親が一緒に療育などに取り組むことで回復した子も多い現実があります。本当に全ての自閉症が先天性なのかは疑問を感じます。
なので、早く親が勉強して、回復する方法を実践していくこと、これが大事だと思うのです。
早期療育がいいと言われている所以ですね。
障害を受け入れてからは前しか見ない!
障害を受け入れて勉強を始めたことで、新たな目標ができました。
それは息子を少しでも回復させること!!!
早急に療育を受け、自分でも勉強したことを実践すること。
可能性が少しでもあるなら実践します。後ろを向いている暇がないくらい、勉強して前しか見れないようにしてしまえばいい、そう考えました。
たった2ヶ月で自閉症の症状が劇的に回復
事実、勉強中に出会った書籍のおかげで、息子は飛躍的な回復をしました!!
たった2ヶ月で驚くくらい多動が減って、会話できるまでになったのです!!
おすすめの書籍
もし自分から勉強しようと行動していなかったら、これらの書籍には出会えなかったでしょうし、息子もここまで回復することはなかったでしょう。
書籍『言葉の遅れが改善する方法』著:片岡直樹

書籍『0~4歳の脳を元気にする療育: 発達障害と改善事例44』著:浅野幸恵

同じ発達障害の子を持つママとの出会いに救われた
息子は発達障害なんだろうなぁと受け入れ出した頃、それでも定型発達の子のママには言えず、友達にも相談できず、話し相手もいなくてずーっと孤独でした。
保育園のママたちにもなんて思われているかわからなくて、怖くて距離を置いていました。
そんな自分の孤独さを、一番救ってくれたのが、同じ発達障害の子供を持つママとの出会いでした。
同じ悩みを抱えるママたちに会う方法
私の場合は、保育園の信頼している保育士さんに紹介してもらえたのですが、療育に通えば同じ悩みを抱えるママと出会えます。
また、お住まいの地域の自治体などで、同じ悩みを抱える親の会を開いてくれている場合もありますので、是非とも検索してみてください。
探し方: 「(お住まいの地域名) 発達障害 親の会」「(障害種別名) 親の会」などでインターネット検索したり、発達障害者支援センターや医療機関に問い合わせてみましょう。
一人で抱え込まず、まずは話しやすいと感じるところにアクセスしてみてください。相談することで、気持ちが楽になったり、具体的な解決策が見つかったりすることがあります。様々なサポートを活用しながら、お子様との日々を少しでも穏やかに過ごせるようになることを願っています。



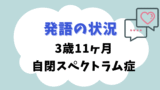

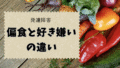

コメント